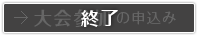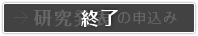大会テーマ「音・音楽からのメッセージ~人とつながる地域とつながる~」に基づいて、今回の講習会は次の3本の大きな柱から成り立っています。
1つ目は、音楽療法における「音や音楽の役割」を再認識する一連の講習です。2つ目は「地域や行政」と音楽療法との連携、あるいは「他職種」と音楽療法との連携を考えるような一連の講習です。さらに3つ目は「音や音楽の役割」を実際に体験するワークショップです。それぞれの柱に詳しい方々を講師としてお招きし、この千葉県で行なわれる大会テーマにふさわしい講習会になるよう企画しました。皆様の積極的なご参加を期待しています。
講習会プログラム
| 時間 |
講習会Ⅰ
音楽療法における
「音や音楽の役割」 |
講習会Ⅱ
「地域や行政」と
音楽療法との連携 |
特別講演/
ワークショップ
「音や音楽の役割」の体験 |
第1講
13:00
|
14:30 |
Ⅰ-1
「フレイル」高齢者に行なう音楽療法について
甲谷至
(神奈川リハビリテーション病院歯科口腔外科) |
Ⅱ-1
「音楽療法士と他職種・行政・地域との連携について」
西巻靖和
(独立行政法人国立病院機構まつもと医療センター統括診療部療育指導科) |
特別講演
「音楽の持つ力」
※会員枠100名
湯川れい子
|
第2講
14:50
|
16:20 |
Ⅰ-2
「音楽療法臨床における『音楽』と『関係』」
生野里花
(東海大学教養学部芸術学科、野花ひととおんがく研究舎) |
Ⅱ-2
「地域に根付く発達障害児への支援モデルと音楽療法士の雇用の関係」
小田知宏
(NPO法人発達わんぱく会) |
W-1
「The リズム」
現場で活かせるリズムフィーリングを声や身体で体験しましょう
※定員40名
B.B.モフラン
(ビタシカオフィス ムジカトゥッティ・エグゼクティブアーティスト) |
第3講
16:40
|
18:10 |
Ⅰ-3
人とつながる、社会とつながる核としての音楽
~音楽中心音楽療法理論や最新の知見の紹介~
鈴木琴栄
(コロンビア大学付属病院 児童精神科) |
Ⅱ-3
音楽療法とスーパービジョン
~実践を支える手だてとして活かすには~
小柳玲子
(調布市社会福祉協議会) |
W-2
「The リズム」
現場で活かせるリズムフィーリングを声や身体で体験しましょう
※定員40名
B.B.モフラン
(ビタシカオフィス ムジカトゥッティ・エグゼクティブアーティスト) |
*やむを得ず時間、内容が変更されることもございますので、ご了承下さい。
*申込み順に受け付けをいたしますので、ご希望の講義やワークショップを受講できない場合があります。
特別講演
「音楽の持つ力」
湯川れい子 音楽評論家・作詞家・日本音楽療法学会理事
人間の五感で、最初に発達するのが聴覚であり、最後まで残る感覚器官もまた聴覚だと言われています。つまり私たちが生命として、母親の胎内に宿ってから20週目くらいには音が聞こえるようになり、5ヶ月もする頃には、母親の心臓の鼓動や、外から聞こえて来る音に、かなり敏感に反応していると言うことなのです。音楽を「音」と「リズム」として考えると、私たちの生命は、すでに産まれる前から音楽の影響を受けていると言う事になります。実際に、その影響にはどんなものがあるのか。単に「音」や「リズム」だけではなく。歌われたり演奏されたりする音楽に、私たちはどう反応し、どんな結果が生じているのか、本当に興味は尽きません。すでに音楽療法の歴史は古く、アメリカやイギリスなどの国で、音楽が医療の現場で使われるようになってからでも半世紀以上。さまざまな専門分野での結果や確証(エビデンス)が得られていますが、私たちは療法士では無く、音楽ファンとして、そんな音楽をもっと多角的にとらえて、日常生活や社会の中で、音楽とどう上手に関わって「音」を「たのしむ」ことが出来るか、そんなお話をしたいと思います。
※この特別講演は千葉・市県民向けセミナー(一般公開)としても開催されます。本学会の会員の受講には他枠の講習会と同様の申し込みが必要です。受講することにより他枠の講習会と同様のポイントを取得することができます。但し、申し込み先着順にて100名です。