
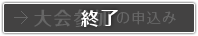
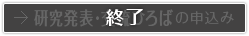
| 講習会申込期間 | 締め切りました。 |
|---|---|
| 地方会申込期間 | 締め切りました。 参加をご希望の方は 当日受付をご利用ください (地方会のみ) |
実行委員長 園川 緑
関東支部会員の皆様、地方会が近づいてまいりました。今回の地方会では、"音楽療法交流ひろば"を開催致します。従来の研究発表とは別枠で、それぞれの地域で実践されている音楽療法について気軽に発表し、話し合える場をランチトークとして設定します。音楽療法に関する事柄について、自由に何でも語り合いましょう。活動内容はもちろんのこと、現場スタッフとの連携、労働条件、研修会等についても、楽しく気軽に語れる場になればと思います。詳しくは企画からの案内をご参照の上、皆さまご参加下さい。
日頃一人で奮闘している音楽療法士の他、他の職種の方々のご参加もぜひお待ちしております。
| 8:30〜 | 受付 | ||||||
| 9:30〜9:45 | 開会式 ハンドベル演奏(演奏:文京学院大学) |
楽 器 ・ 書 籍 等 販 売 |
|||||
| 9:45〜10:25 | 大会長講演 :師井和子 「新たな音楽療法のあり方を考える」 |
||||||
| 10:30〜12:00 | 特別講演 :成瀬悟策(九州大学名誉教授) 「音楽療法と動作」 |
||||||
| 12:00〜13:00 | 昼食休憩 | 支部幹事会 | 大会企画♪ランチトーク♪ 音楽療法交流ひろば 〜地域での実践紹介〜 |
||||
| 13:00〜13:30 | 支部総会 | ||||||
| 13:40〜 | 研究発表 13:40〜14:40 ・口頭 ・ポスター発表 |
||||||
| 14:00〜16:30 | シンポジウム ひとつの音からの出発 〜これからの音楽療法を考える〜 「専門職として最も大切にしていること、 これからの音楽療法に期待すること」
|
||||||
| 16:30〜17:00 | 閉会式 | ||||||
| 〜17:30 | クローク終了 | ||||||
師井 和子 (NPOあいね代表理事)
これまでの音楽療法のほとんどは、「日常の中で非日常の世界を展開」することで治療的効果を得ようとしてきました。被災者支援や危機状態にある人々への支援はどうなのでしょうか?ここで被災者支援に取り組んだ音楽療法の事例を紹介し、これまでの音楽療法との違い・役割・可能性など検討し、新たな音楽療法のあり方を探りたいと思います。
<プロフィール>
1997年米国音楽療法協会認定音楽療法士(MA-CMT)取得、NPO法人あいね代表理事、東京都スクールカウンンセラー、東海大学非常勤講師。著書「心にとどく高齢者の音楽療法」「心をつなぐ音楽回想法」、訳書「GIM(音楽によるイメージ誘導法)におけるセッションの進め方」他
成瀬 悟策(九州大学名誉教授)
<プロフィール>
1924年:岐阜県に誕生。1950年:東京文理科大學・心理学科卒業。1969年:九州大学教授・1988年:同大学名誉教授。1989年:九州女子大学長、日本心理臨床学会初代理事長。初代以来、日本臨床動作学会理事長。
司会:師井和子
音楽療法と関わりの深い4名の専門職の方々からお話しいただきます。まず被災者でありながら被災者支援活動に尽くされている看護師の立場から、次に長年心と体の問題を抱えた患者さんと向き合ってこられた心療内科医の経験から、そして作業療法士育成に情熱を傾けられている教育者の立場から、最後に地域福祉に取り組まれている経済学博士の視点から「現場で専門職として最も大切にしていること」と「これからの音楽療法に期待すること」をお話し、ご提言いただきます。外部の専門職の方々からの貴重なご意見から、今後の音楽療法発展のために何らかのヒントを探っていただくことに大きな期待を寄せています。
音楽療法を学んでいる方、関心のある方ならどなたでもご参加ください!各自、昼食を持ち寄り、交流を深めながら情報交換したり、音楽療法について語り合う楽しい時間を過ごしてみませんか?名づけて♪ランチトーク♪としました。研究会や勉強会の実践、地域における個人の音楽療法活動を大いに語り合いましょう。
発表形式は自由(ポスター、パソコンの使用可)。発表なし、"トーク"だけ、聞くだけのご参加もOKです。この場合、申し込みはいりません。
発表を希望される方は、「交流ひろば申込原稿様式」ファイルをダウンロードし、必要事項を記入の上、下の申し込みボタンよりお申込みください。登録手続き終了後、自動配信メールにて受理通知が送信されます。なおこの発表は、認定申請の際のポイントにはなりません。
申し込み期間は、
2012年(平成24年)10月23日(火)9:00より11月22日(木)15:00まで。
必着厳守です。
*インターネットのみの受付となりますのでご注意ください。
*発表時間等の詳細については、後日お知らせいたします。